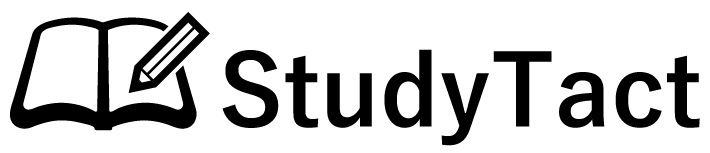世田谷区で中学受験の塾をやっております末廣です。
三児の父をやっております。
ということで、今回は、ちょっと皆さんとはテイストを変えて、「未就学児にひらがなを教える方法」について書いていきたいと思います。
実際、長女はこの方法で幼稚園に入る前にひらがなを習得しました。次女はこれからチャレンジです。
下準備
- 鉛筆の持ち方
職業柄、気になってしまいます。鉄は熱いうちに打てということで、後から直すのも大変ですし、初めからきちんとした握り方をマスターしておきましょう。 - あいうえおに興味を持つ
お風呂でも家の壁でも、どこでもOKですが、「あいうえお」に対する興味は大人の方で喚起しておくことが大切です。興味喚起については、無駄になることを前提に!何より大人が楽しむことを忘れずに!
さてここからが本題です。まずは、「白紙」を用いましょう。
決して、□があってその中に書かせようとしてはいけません。
だって、□があると「よく書けたね。でもちょっとはみ出してるかな。次は□の中にちゃんと書いてみよう」って勝手にハードルを上げたくなりますから(笑)
幼児期に「ちゃんと」は必要ありません。「書く」という行為に集中させてあげましょう。
あいうえお表を見ながら書いていきましょう。音を頼りに「けはどれだ?」と探すだけでも、子どもにとっては楽しい作業に変わります。
大人が欲張って、「今日は○ページ」なんて考えてはいけません。どのみち計画通りになんて行かないのですから(笑)
「あ」から始める…たぶんこれがつまずきの原因だと思います
幼児期の子どもの世界は、とにかく「具体」が全てです。
「母音」とか「子音」とか、そんなものはありません。ですから、「あ」から始める必要性はないのです。「身近にあるものを書けた」この達成感を利用するのが最も効果的だと思います。
汚くても全く問題ありません。同じ字を何回も連続で練習させられるよりも、子どもも楽しく取り組んでくれるはずです。
ある程度かけるようになったら、しりとりをしてみましょう。必然的に同じ字を繰り返し書くことになります。
「繰り返し書かせよう」という大人の意識が書くことを面白くないものにしてしまいます。
あくまで楽しんで取り組む一環として、しりとりを活用してみましょう。
補足
ここで、疑問に思った方もいるでしょう。
この方法では習得できない文字もあるのでは?
という疑問です。
正直に言えば、あるかもしれません。でも少し考えてみてください。幼稚園に入る前の子がひらがなを書こうとしているわけです。「完璧」である必要はあるのでしょうか?また、「書く喜び」を体験した子は、今度は「きれいに書きたい」というように、欲求が昇華していくはずです。この段階で、市販のドリルなどを使っていけばよいでしょう。
ひらがなに関して、ブログにも書いていますので、もしお時間があればどうぞ。
https://keio-juku-gakudo.hatenablog.jp/entry/2018/07/14/174150
この勉強法が参考になったら…