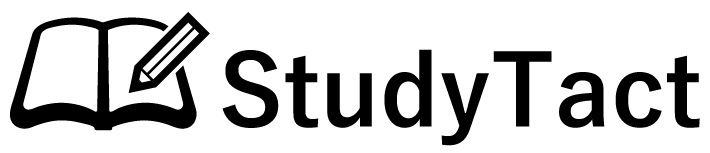こんにちは
学習塾智心館の谷畑(やばた)です。
みなさんは暗記、好きですか?
イエスと答える方はあまりいないのではないでしょうか?“暗記=闇雲に覚えなければならないもの”として、ネガティブイメージを持たれている方が多いと思います。
私は暗記が得意でした。
徳川幕府の全将軍を暗記して、「ドヤ!」と家族や友達に自慢する、いけ好かない野郎でした(不快な思いをさせた皆さん、その節はすませんでした笑)。
今回は「暗記法」を語る上で、一番大前提となる、頭の中の話をしようと思います。
なんなら「法」でもないかもしれません。
私の頭の中で起きている話です。実体がありません。
ですが、まずそもそもの覚え方を理解しさえすれば、オレンジペンを使うだ、英単語帳●●回繰り返すだは、おのおの自分に合う方法を試していけばいいだけだと思うのです。
私が提案するのは、4つの関連づけです。
- 1つ目は音との関連づけ。
- 2つ目はイメージとの関連づけ
- 3つ目はチャンク
- 4つ目は日常との関連づけです。
まず1つ目の音との関連づけ。
これは英語が苦手な生徒に顕著です。「英単語覚えられませ〜ん」は、単語と読みの不一致による場合が少なくありません。
読み方が分からないまま、なぞるように書いている。発音とスペルが一致しないまま字面で覚えた気になっている。
それではせっかくの努力が時間の無駄となってしまう可能性が高いです。
頭だけ使っている状態は生物として不自然です。
生き物は五感をフルに使って行動します。目から得る情報だけでなく、口から発し、耳からも情報を得る。
皆さんもきっと掛け算九九は、字面で文字情報を追っかけたのではなく、音から入って暗記したのではないでしょうか?
何かの替え歌で覚えるなどもよくありますよね。
これらは生き物として当たり前の行動なのです。
2つ目はイメージとの関連づけです。
例えば、ownという英単語(英単語ばっかりですいません)。「自分自身のー」という意味ですが、私はサッカーのオウンゴールとイメージを紐づけています。まさに「自分自身のゴールに入れる」というイメージから。
このように無機質な語句同士に繋がりを持たせるのです。この流れでいうと、理科や社会の勉強法でよく見るメモリーツリーなどもこの関連づけの一つですよね(何それ!という方は是非ググってみてください)。
3つ目はチャンク。
バラバラのものを1つの塊にすることをこう言います。
例えば電話番号を覚える際には11桁丸暗記するのではなく、080ー□□□□―△△△△と三つの塊に分けて覚えてはいませんか?
このように記憶を意味のある塊にまとめて覚えると、思考の整理整頓ができて、知識を取り出しやすくなるのです。
ここでも例をあげましょう。
中学生が苦手にしやすい、鎌倉仏教。これも塊にすると記憶の定着がスムーズです。
これで法然ー親鸞という塊ができました。
どうでしょうか?あとはこの塊の中から、必要な情報を適宜取り出せばいいのです。
もちろん努力をゼロにできますよ!と言える話ではありませんが、ちょっとだけでも暗記の絶対量は減るのではないでしょうか?
最後に日常との関連づけです。
どういうことか?勉強そのものを日常に組み込んでいっちゃえばイイじゃん!という驚愕の話です笑
ではどのようにするのか?勉強する敷居を下げるのです。
受験生ならトイレに公式を貼ったり、お風呂で暗唱したりするといい!なんて話は聞いたことあるのではないでしょうか?
何も机の上だけが勉強ではありません。
寝る前に今日学んだことを思い返してみる。ふとした瞬間、過去に間違った数学の解法を頭で解き直してみる。友達や家族に学んだことを伝えてみる(実際に教えている“つもり”で勉強しているだけでも、効果が見られるらしいですよ!)。
このような些細なことの積み重ねで、“勉強思考”は完成します。
あいつ、たいして勉強してないのにできて羨ましいなぁ!
そんな彼、彼女らは普段の生活からそのような思考を(無意識かもしれないけれど)実践しているからこそ、効率よく知識を吸収しているのです。
だから同じ時間勉強し、同じ授業を受けたとしても差が出てくる。
であればあなたも、まずは無意識を意識することから始めてみませんか?
この勉強法が参考になったら…